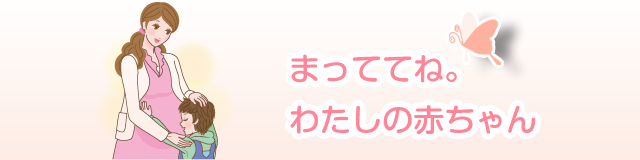妊娠中期以降に行われる検査
分泌物検査
妊娠の中期から後期(24~37 週頃)に、産道の細菌検査が行われます。
産道に細菌が繁殖している場合には、出産時に赤ちゃんに細菌がうつることがあります。
とくに、出産で赤ちゃんが感染しやすい菌は、B 群溶血性連鎖球菌(Group B Streptococcus, GBS)と性器クラミジアです。
GBS感染症について

人間の体内には、部位や臓器ごとに細菌集団が住みついています。これらは「常在菌」とよばれ、病気を起こすどころか、病気を引き起こす細菌から人間を守っています。
産道(膣)の常在菌の1つがGBSで、ほとんどの場合、GBS に感染しても病気にはなりませんが、GBS 検査が陽性で、GBS 抗体価が低い場合には、赤ちゃんに感染し、重い症状がみられることもあります。このような場合には、陣痛が始まったら予防的に抗生物質を投与し、赤ちゃんが感染しないような治療を行います。
この検査は一般的に妊娠24週から37週までの間に行われます。
性器クラミジア検査について
クラミジアは感染しても女性の場合はほとんど症状がないため、気がつかない人が多いのですが、クラミジアに感染すると前期破水(お産にならないのに卵膜が破け、破水してしまうこと)がおきたり、早産しやすくなります。
また、赤ちゃんが産道を通る際に感染し、肺炎や結膜炎を起こすこともあります。クラミジア感染は、抗生物質を1~2週間のむと、ほとんどの場合、完全に治ります。
この検査は一般的に妊娠30週頃までに行われます。
HTLV-1 抗体検査
ATL(成人T 細胞白血病)の引き金となるHTLV-1というウイルス感染を調べる検査で、妊娠30週頃までに行われます。
なぜ?
このウイルスに感染していても、若いうちは症状がなく、50~60歳くらいになってから白血病を発症する人が多いようで、妊婦さんの場合には気がつかないことがほとんどです。しかし、症状がなくても体内にウイルスがいると、母乳を介して赤ちゃんに感染する危険があります。
感染していたら?
血液中の免疫抗体の有無を調べると、体内にウイルスがいるかどうかがわかるので、出産後の授乳方法を前もって検討することができ、母乳を介した感染を未然に防ぐことが可能になります。注意:以前は、西日本に多く蔓延していましたが、最近では全国的に広がる傾向がみられています。
血算検査(貧血の検査等)
妊娠24 週から35 週までの間に1 回、妊娠36 週以降に1 回、妊娠初期と同じように、貧血の検査を主な目的として血算検査が行われます。貧血がある場合には、食事や鉄剤での鉄分の補給が必要となります。
血糖検査

妊娠24 週から35 週までの間に、妊娠初期と同じように、血糖値を調べる検査を行います。血糖値が標準値より高い場合には、75gのブドウ糖を溶かした水を飲み、1時間、2時間後の血糖値を測り、より詳細な診断を行います。糖尿病(妊娠糖尿病、糖尿病合併妊娠)の場合には、妊婦にもおなかの赤ちゃんにも良くない影響がみられるため、食事やインスリンで血糖値が高くならないような治療を行います。