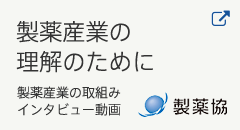内部統制基本方針
キッセイ薬品内部統制基本方針
キッセイ薬品工業株式会社は、「純良医薬品を通じて社会に貢献する/会社構成員を通じて社会に奉仕する」という経営理念の下、役員及び従業員が総力を挙げて企業価値を向上させ永続的発展を目指すとともに、社会的責任を果たすことをここに宣言する。本基本方針は、会社法に従い、当社の内部統制システムの体制整備のために取り組む活動の基本方針を定めるものである。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するための体制
1) キッセイ薬品行動憲章に則り、企業倫理・法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。又、取締役会は、コンプライアンス推進部⾨責任者をして、コンプライアンス推進を統括せしめると共に、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置する。尚、コンプライアンス委員会の委員長は、コンプライアンス推進部⾨の長とする。
2) 取締役会は、取締役、監査役並びに従業員がコンプライアンス上の問題を発見したときの報告及び迅速かつ適切な情報の収集、確保を行い適切な対応がとれる様、内部通報者保護法に従い、法務部⾨責任者をして、通報・相談制度を構築し、特に取締役との関連性が高いなどの重要な問題は、直ちに取締役会、監査役に報告されるよう体制の整備を行う。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 取締役会は、当社の取締役及び部門責任者の職務執行に係る情報の保存及び管理を適切に行う体制を整備する。又、法務部門責任者をして、文書管理規程を運用せしめ、これにより、必要な文書(磁気的記録その他の記憶媒体を含むものとする。)を関連資料その他情報と共に、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
2) 文書管理規程に定める文書について、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合に遅滞なくその閲覧に供する。
3) 文書管理規程の制定及び改定をするときは、事前に監査役会の意見を求め、取締役会の承認決議を得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 取締役会は、リスク管理規程その他の必要な社内規程を定め、業務執行に係るリスクの把握と管理を行う体制を整備する。
2) リスクの適切な抽出、評価及び対応を期すことを目的として、会社のリスク及び危機管理を経営計画に対する個別のリスク、法的リスク及び危機管理、その他の危機管理の3つの領域に分けて適切な部門に管掌させる。又、当社は、取締役会の諮問機関としてこれら3部門の部門責任者を含むメンバーからなるリスク管理委員会を設置し、定期的にリスク管理体制整備の進捗状況を監視すると共に、具体的な個別事案の検証を通じて全社的体制の妥当性に関する検証を行う。尚、リスク管理委員会の委員長は、取締役社長が任命する。
3) 各部門責任者は、リスク管理規程に従い、予め具体的なリスクを想定・分離し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達とその対応体制を整備すると共に、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成を行う。又、新たに発生したリスクについては同規程に従い遅滞なくリスク管理委員会に報告し、適切に対処する。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 当社における一定基準以上の全ての事業は、その計画及び実施の段階において、取締役会又は関係する取締役及び部門責任者その他の機関により、定期的或いは随時に適正かつ十分な科学的根拠により検証され、必要な修正がなされなければならない。
2) 取締役の職務執行の効率性を高めるために、連携と牽制とを意図して社内組織を構築し、社内規程の定めに基づく明確な業務分掌、職務権限及び意思決定手続きを設け、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。
3) 取締役会は、取締役及び従業員が共有する全社的な計画を策定し、各事業年度の半期毎に各部署が実施すべき合理的かつ具体的な目標並びに効率的な達成方法を定める。又、効率化を阻害する要因を排除するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する体制を構築する。
5.企業集団における業務の適正を確保する体制
1) キッセイグループ行動憲章を定め、これに則り、グループ企業の取締役及び従業員が一体となって遵法経営を行う。
2) 当社は、取締役会において関係会社管理規程等を整備し、一定の事項について各グループ企業の取締役会決議前に当社関連企業管理部門に承認を求め又は、報告することを義務づけ、必要に応じ当社取締役会の事前の承認決議を得るものとする。又、当社における管理領域毎に、効率性向上のための施策を検討・実施する。
3) グループ全体の通報・相談制度を設け、法律違反及び社内規則違反等に関する情報の収集、確保に努め、グループ各社における自浄機能により、未然に適切な対応がとれるようグループ全体の遵法経営体制を整備する。
4) グループ企業は、その業態やリスクの特性に応じた適切なリスク・マネジメントを行い、当社は、グループ企業のリスク・マネジメント全般を掌握し、助言、指導等の必要な施策を実施する。
5) グループ企業の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう、グループ企業の業務分掌、職務権限及び意思決定に関する明確な手続きを整備する。
6.財務報告及び非財務情報の開示の信頼性を確保するための体制
1) 財務報告等に係る内部統制構築・評価の基本方針を定め、適切に運用することにより、グループ全体の財務報告及び非財務情報の開示の信頼性を確保する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人にかかる体制とその独立性に関する事項
1) 監査役は、職務を補助すべき使用人が必要な場合、速やかに取締役社長と協議の上、補助者として内部監査部門の従業員を使用することができる。
2) 監査役より、監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関する限り取締役、内部監査部門の長らの指揮命令を受けない。
3) 補助者に任命された従業員の人事異動、人事考課、懲戒処分は、その内容につき、監査役会の事前の承認を得なければならない。
8.当社の取締役及び使用人並びにグループ企業の取締役、監査役及び使用人による監査役又は監査役会に対する報告のための体制、その他監査役監査の実効性確保のための体制
1) 当社並びにグループ企業の取締役会は、監査役会に報告すべき事項を監査役と協議の上定め、当社取締役、部門責任者又は、グループ企業の取締役等が報告をする。
2) 監査役会に対して、代表取締役と定期的に意見交換を行う機会を与えるほか、その要望に応じ、取締役及び従業員に対するヒヤリングを実施する機会を与える。
3) 監査役会に対して、独自に弁護士及び公認会計士を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証する。
4) 監査役又は監査役会へ報告を行った当社及び、グループ企業の取締役・従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
5) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い速やかに行う。
9.反社会的勢力及び腐敗行為を排除するための体制
1) キッセイ薬品行動憲章に則り、反社会的勢力及び団体との一切の関係を排除するための社内体制を整備する。
2) 腐敗行為禁止基本方針に則り、誠実・清廉な企業文化の陶冶に努め、法令・社会規範を遵守し、且つ、公正な取引と健全な競争を事業の基本として、贈賄を含む、如何なる腐敗行為を事業活動から排除する。
財務報告等に係る内部統制構築・評価の基本方針書
第1章 財務報告に係る内部統制の構築・評価の基本方針
1.基本方針
内部統制報告制度への対応を当社グループの企業基盤強化の体制整備の一環として位置づけ、金融商品取引法上求められている財務報告に係る内部統制(以下内部統制という)の構築及び評価を図る。
2.目的
金融商品取引法第24条の4の4の規定に基づく内部統制報告制度における内部統制の構築及び評価を行う際の基本的事項を定め、会社の財務報告の信頼性を確保することにより投資者の信頼を確保する。
3.構築の基本的計画及び方針
キッセイ薬品内部統制基本方針を踏まえ、会長は内部統制を全社的レベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施するための基本的計画及び方針を定める。
4.適正な財務報告を実現させるために適用する原則
適正な内部統制を構築及び評価するための基準は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(令和5年5年4月7日企業会計審議会)に準拠する。
5.適正な財務報告を実現させるために構築する内部統制の範囲
内部統制を構築する範囲は、基本的には、すべての事業拠点を対象とするが、当該報告制度が求めるところの評価範囲に準ずる。
又、構築の対象とする範囲は、そのすべてではなく、重要性の判断基準に基づき決定した範囲とする。
6.適正な財務報告を実現させるために構築する内部統制の水準
一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、すべての重要な点において、財務報告が適正に行なわれているといえる水準まで構築をする。
7.内部統制の構築及び評価の責任者
内部統制の構築及びこれらの評価に関する責任者は、内部統制報告書の提出者である会長とする。
内部統制の責任者である会長は、財務報告に関する開示すべき重要な不備があった場合並びに内部統制の重要な役割を担う者による不正及び重要な内部統制の変更があった場合は、監査役会及び会計監査人に迅速に報告する。
8.内部統制の構築及び評価の体制
(1) 内部統制の構築の体制
- 内部統制報告制度の構築は、財務管理部が統括して推進する。
- 内部統制の構築の運営責任者は、財務管理部長とする。
- 内部統制の構築は、業務プロセスの各主管部署の管理者(以下プロセスオーナーという)及び関係部署の管理者がその責任の下に当該部署の業務として推進する。
- 内部統制は、当社グループ全体に及ぶものであり、経営企画部はグループ各社の窓口として事務的な連携を取る。
(2) 内部統制の評価の体制
- 内部統制報告制度の内部統制の整備状況及び運用状況の評価は、監査室が行う。
- 会長は、内部統制評価の実務責任者として監査室長を指名する。
- 監査室長は、評価に当たり必要と考える場合は、関係部署から適宜に人材の応援を求めることができる。
- 内部統制の評価は、当社グループ全体に及ぶものであり、子会社の重要な統制の評価についても親会社(当社)の監査室が行う。
9.内部統制の構築及び評価のための教育訓練
内部統制の構築・評価に関しては相応の専門的知識が必要となることから、制度の理解のための教育訓練を適宜に実施する。
教育訓練は、以下のメンバーに対して適宜に実施する。
(1) 経営者・取締役・監査役・部門長(連結子会社を含む)
(2) プロセスオーナー、担当者及び従業員(同上)
第2章 財務報告に係る内部統制の構築の方針
Ⅰ.リスクの識別と評価
財務報告に重要な影響を与える可能性のあるリスクを的確に識別し、対応することによって、財務報告の信頼性を確保できる体制を構築する。
期初にリスクの評価を行い、期末までに状況の変化がないかを確認する。
リスクの識別に関する文書化は、「リスクカタログ評価シート」に必要事項を記載する方法で行う。
1.識別するリスクの定義
識別するリスクは、財務報告の信頼性を阻害する要因すなわち虚偽記載リスクとする。リスクには以下の外部的・内部的要因など様々なものが挙げられるが、ここではそれらのうち、組織に負の影響を与えるものに限定するとともに、その中でもさらに財務報告に影響を与えるものに限定する。リスクの評価の対象には、不正に関するリスクも含まれる。
外部的要因 : 天災、盗難、市場競争の激化、為替や資源相場の変動など
内部的要因 : 情報システムの故障・不具合、会計処理の誤謬・不正行為の発生、個人情報及び高度な経営判断に関わる情報の漏洩など
2.リスクへの対応
すべてのリスクに対応することは現実的に不可能であるため、財務報告に重要な影響を与える可能性のあるリスクに限定して対応する。
3.リスクの識別と分類の方法
財務管理部は、想定しうるリスクを詳細に展開した「リスクカタログ評価シート」を作成し、その発生可能性、影響度、リスクの重要性などを識別する。
又、「リスクカタログ評価シート」により下記の分類をする。
| 全社的対応 | 財務報告全体レベルに影響するリスク |
|---|---|
| 業務プロセス対応 | 個別の財務報告項目レベルに影響するリスク |
4.リスクの評価方法
(1) 発生可能性の判断基準
発生可能性について、3段階で評価する。
| 1 | (低)・・・可能性小 ほとんど発生しない 年1回程度発生する可能性がある |
|---|---|
| 2 | (中)・・・可能性中 たまに発生する可能性がある 半年に1回程度発生する可能性がある |
| 3 | (高)・・・可能性大 たびたび発生する可能性がある 月1回程度発生する可能性がある |
(2) 影響度の判断基準
影響度について、3段階で評価する。
| 1 | (低)・・・影響度小 財務報告に与える金額的影響がほとんどない |
|---|---|
| 2 | (中)・・・影響度中 財務報告に与える金額的影響がある |
| 3 | (高)・・・影響度大 財務報告に深刻な金額的影響を及ぼす |
(3) リスクの重要性の判断基準
上記の発生可能性及び影響度を勘案して、重要度を算定する。
| 発 生 可 能 性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 影響度 | 1 | 小 | 小 | 中 |
| 2 | 小 | 中 | 大 | |
| 3 | 中 | 大 | 大 | |
- ① 大及び中のリスクに対応する業務プロセスを評価対象として決定する。
- ② 小に対しては、その理由を明示した上で、評価対象から除く。
(4) 評価結果の報告
識別され分類・評価したリスクは、遅滞なく会長及びリスク管理委員会に報告する。
Ⅱ.全社的な内部統制の構築
財務報告に係る虚偽記載リスクのうち全社的なリスクについて、適切な対応を図るべく全社的な内部統制を構築する。
前年度末の財務数値が確定した段階で、当年度の予測値を考慮して、金額的及び質的影響の重要性の観点から文書化範囲及び評価範囲を決定する。
又、業務プロセスレベルでのリスクに対応するべく、業務プロセスにおける内部統制が適切に機能するように、全社的な内部統制が適切に支援する体制を構築する。
1.全社的な内部統制の文書化方法
主管部署は「全社的な内部統制コントロールシート」の評価項目に不足がないことを確認した上で、評価項目に回答することで整備状況の確認を行う。整備状況が良好でない部分については、内部統制の体制等を構築するものとする。財務管理部は、評価項目に係る各プロセスオーナー及び関係部署の管理者に、質問及び具体的な資料の査閲を行うことにより、整備状況を確認する。
2.全社的な内部統制の整備状況の評価項目
実施基準に記載されている42項目を参考に「全社的な内部統制コントロールシート」の評価項目を決定し、組織の改編時などには随時に見直しを行う。
3.全社的な内部統制の整備状況の文書化ツール
「全社的な内部統制コントロールシート」を利用する。
親会社(当社)はシートの全項目における文書化を行い、連結子会社は、適宜に評価項目を選定した連結子会社用のシートを作成した上で文書化を行う。
4.全社的な内部統制の事業拠点の定義
事業拠点とは、親会社(当社)、連結子会社及び事業等を勘案し選定した、内部統制の構築・評価を行う単位をいう。
5.全社的な内部統制の文書化対象事業拠点の選定
基本的には、すべての事業拠点を文書化の対象とする。但し、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものは、評価対象としない。また、評価対象外の拠点で重要な不備等が識別された場合は、当該不備等が発生した事業年度において評価対象に含めるものとする。
金額的影響の重要性が僅少であるとする基準については、次の要件の何れかにより判断するものとする。
| 1 | 連結決算において、連結消去後の税引前利益を金額の高い会社から順に積み上げ、累計金額が全体の95%に入らない事業拠点 |
|---|---|
| 2 | 連結決算において、連結消去後の売上高を金額の高い会社から順に積み上げ、累計金額が全体の95%に入らない事業拠点 |
金額的影響の重要性の判定は、負の数を含めた単純数値によるものではなく、絶対値による。
Ⅲ.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の構築
決算・財務報告プロセスにおける重要な虚偽記載リスクを低減できる内部統制を構築する。
文書化範囲及び評価範囲の決定は、全社的な内部統制に準ずる。
決算・財務報告プロセスには、全社的な観点で評価すべきものと個別の業務プロセスとして評価すべきものとがある。全社的な観点で評価すべきものは全社的な内部統制に準じ、個別の業務プロセスとして評価すべきものは業務プロセスに係る内部統制の構築に準ずる。
1.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の文書化方法
主管部署は「全社的な観点での評価シート」の評価項目に不足がないことを確認した上で、評価項目に回答することで整備状況を確認する自己点検を行う。整備状況が良好でない部分については、内部統制の体制等を構築するものとする。財務管理部は、評価項目に係る各プロセスオーナー及び関係部署の管理者に対する質問及び具体的な資料の査閲を行うことにより、整備状況を確認する。
2.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備状況の評価項目
全社的な観点で評価すべきものは「全社的な観点での評価シート」に明記した評価項目とし、個別の業務プロセスとして評価すべきものは「評価対象項目の識別リスト」により重要性を検討し評価項目を選定する。組織の改編時などには、主管部署と連携して随時見直しを行う。
3.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備状況の文書化ツール
「全社的な観点での評価シート」を利用する。
親会社(当社)はシートの全項目における文書化を行い、連結子会社は、適宜に評価項目を選定した連結子会社用のシートを作成した上で文書化を行う。
4.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の文書化対象事業拠点の選定
全社的な内部統制において選定した事業拠点とする。
Ⅳ.業務プロセスに係る内部統制の構築
財務報告における重要な虚偽記載リスクを低減できる内部統制を構築する。
前年度末の財務数値が確定した段階で、当年度の予測値をもとに金額的影響、リスクの発生可能性並びに質的影響を考慮して文書化範囲及び評価範囲を決定する。
基本的には現状の内部統制の整備状況を確認し、リスクに対応した統制が備わっていない項目について、財務管理部とプロセスオーナー・担当者との協議の上で整備すべき統制をまとめ、有効な水準の内部統制を構築する。
1.業務プロセスに係る内部統制の文書化方法
主管部署は、主要な業務プロセスごとに「業務フロー」「業務記述書」「リスク・コントロール・マトリクス(RCM)」「職務分掌表」を作成する。更に各業務におけるリスクに対するコントロールの対応状況を把握し、「RCM(整備状況評価シート)」で虚偽記載リスクの低減化状況の十分性を検討し、文書化する。
「業務フロー」の文書化に当たっては、「業務フロー記述標準」を参考とする。
「職務分掌表」は業務の承認経路を明らかにしたものであり、承認者不在時の対応等については、業務プロセスごとに必要に応じて手順を欄外に記載する。
2.業務プロセスに係る内部統制の整備状況の評価項目
主管部署は、「業務フロー」「業務記述書」「職務分掌表」で明確にした虚偽記載リスクに対して、「リスク・コントロール・マトリクス」の中で、統制目標、アサーション(統制上の要件)と結びつけ、リスク低減の十分性を評価できるようにする。
評価項目は、業務プロセスごとにリスクの重要性を勘案して検討する。
3.業務プロセスに係る内部統制の整備状況の文書化ツール
文書化ツールとして「業務フロー」「業務記述書」「RCM(整備状況評価シート)」「職務分掌表」を利用する。連結子会社は、親会社の文書化ツールを参考に適宜に作成する。
4.業務プロセスに係る内部統制の文書化体制
各業務プロセスのプロセスオーナー・担当者は、「業務フロー」「業務記述書」「リスク・コントロール・マトリクス」「職務分掌表」を文書化する。
財務管理部は、現状の整備状況を「RCM(整備状況評価シート)」を利用して確認する。不備があれば各業務プロセスのプロセスオーナー・担当者は責任を持って是正を行い、再度財務管理部が確認する。
尚、IT業務処理統制には、システムごとにシステム企画部担当者及び委託先であるキッセイコムテック(株)担当者が参加し、自動化統制に漏れがないようにする。
5.業務プロセスに係る内部統制の業務プロセス、サブプロセスの定義
業務プロセスとは、製品やサービスの開発から購買、生産、販売、流通に至る一連の企業活動をいい、法令・規則の遵守、会計・財務報告に関する情報の記録に係る活動を含む。サブプロセスとは、業務プロセスを活動ごとに細分化したものである。
6.業務プロセスに係る内部統制の文書化対象事業拠点の選定
業務プロセスに係る内部統制の文書化の対象とする事業拠点は、以下に定める評価の方針を基本として、会長が選定する。
(1) 重要な事業拠点の選定
| 1 | 重要な事業拠点の判断基準は、連結売上高とする。 |
|---|---|
| 2 | 連結消去後の売上高を金額の高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね3分の2に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点とする。 |
| 3 | 上記金額的影響の大きい事業拠点に加え、質的影響を考慮して必要に応じ重要な事業拠点とする。 |
(2) 全社的な内部統制の有効性の程度による重要な事業拠点の判断基準並びに3分の2の妥当性の判定
全社的な内部統制の有効性に問題がある場合、基本的には、是正措置を講じて有効な水準にすることを前提とするが、是正困難な不備がある場合は、業務プロセスに係る内部統制への影響を検討し、重要な事業拠点の判断基準並びに3分の2の妥当性(拡大の必要性)を判定する。
7.業務プロセスに係る内部統制の対象とする業務プロセスの選定
業務プロセスに係る内部統制の文書化の対象とする業務プロセスは、原則として以下の通り選定する。
(1) 事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスの選定
事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上高、売掛金、棚卸資産とする。但し、他の勘定科目において事業目的に大きく関わる勘定科目につき重要性が大きいと判断された場合には、必要に応じ該当勘定科目を追加検討する。
各勘定科目に至る業務プロセスは、以下の通りとする。
| 1 | 売上高・・・販売プロセス |
|---|---|
| 2 | 売掛金・・・販売プロセス |
| 3 | 棚卸資産・・・購買プロセス、原価計算プロセス、在庫管理プロセス |
(2) 販売プロセス、購買プロセス、原価計算プロセス、在庫管理プロセスの範囲
各業務プロセスにおけるサブプロセスは、以下の通りとする。
| 1 | 販売プロセス・・・受注・出荷・請求・回収・債権管理・値引・割戻・返品・マスタ管理 |
|---|---|
| 2 | 購買プロセス・・・発注・受入検収・返品・マスタ管理 |
| 3 | 原価計算プロセス・・・標準原価設定・原価計算・原価差額調整 |
| 4 | 在庫管理プロセス・・・廃棄・評価減・実地棚卸 |
(3) 事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスのうち、財務報告に対する影響の重要性が僅少であるとして評価対象から除外するための判定
重要な事業拠点において複数事業を営んでいる場合で、重要な事業または業務との関連が低く、財務報告に対する影響の重要性も僅少である業務プロセスは、評価対象から除外する。
(4) 個別に評価対象として追加する際の、重要な虚偽記載リスクの把握と業務プロセスの選定
「リスクカタログ評価シート」において、リスクが高いとして認識された業務プロセスについては、個別に評価対象として追加する。
8.委託業務に係る内部統制の整備状況の確認
委託先に対して、財務報告における重要な虚偽記載リスクを低減できる内部統制が構築されているか確認する。
委託先が別に受けた評価の報告書が利用できる場合はこれを確認し、利用できない場合は、会社が直接サンプリングにより確認する等の方法を検討する。
Ⅴ.IT全般統制の構築
財務報告における重要な虚偽記載リスクを低減できる内部統制を構築する。基本的には、現状の内部統制の整備・運用状況を確認することにより、有効な水準の内部統制を構築する。
業務プロセスの評価範囲が決定された段階で、それに係るシステムの文書化範囲及び評価範囲を決定する。
文書化に当たっては、専門的知識を要する分野であるため、必要に応じて外部専門家のアドバイスを受ける。
1.IT全般統制の文書化方法
(1) IT全般統制は、評価領域(ドメイン)毎の統制活動に応じてシステムをグルーピングし、当該グループごとに文書化を行う。
(2) アプリケーションシステム一覧やコンピュータ環境などを記載した「システム概要ワークシート」を作成し、システムの概要を把握する。
(3) IT全般統制の「リスク・コントロール・マトリクス」を作成することにより、IT全般統制におけるリスクとその低減化状況を把握する。
2.IT全般統制の評価項目
IT全般統制の「リスク・コントロール・マトリクス」に記載されている統制のポイント、統制活動を参考にIT全般統制の評価項目を決定し、IT全般統制の「リスク・コントロール・マトリクス」を変更した時などには、主管部署と連携し随時見直しを行う。
3.IT全般統制の文書化ツール
IT全般統制の「リスク・コントロール・マトリクス」を利用する。
4.IT全般統制の文書化分野
IT全般統制は、以下の評価領域(ドメイン)ごとに文書化を行う。
- ① システムの開発に係る管理
- ② システムの変更に係る管理
- ③ システムの運用に係る管理
- ④ アクセス管理
5.IT全般統制の文書化単位の識別
文書化範囲として選定された業務プロセスにおいて、システムにより自動化された業務処理がある場合は、当該システムの評価領域(ドメイン)の状況を把握し、その概要を基にIT全般統制の文書化単位を識別する。
第3章 財務報告に係る内部統制の評価の方針
Ⅰ.評価計画の策定
財務管理部は、前年度末の財務数値が確定した段階で、評価の対象となる事業拠点及び業務プロセスを再検討し、当年度の評価の範囲を決定する。監査室は、それに基づいて評価の実施体制、実施時期等の年間スケジュールを策定する。
Ⅱ.リスクの評価と対応体制の評価
1.リスクへの対応方針
すべてのリスクに対応することは現実的に不可能であるため、財務報告に重要な影響を与える可能性のあるリスクに限定して対応する。
企業の置かれた環境の変化に応じて、対応すべきリスクに変化があることを十分に留意する。
2.リスクの評価方法
主管部署は、毎期期首に、前年度に識別した「リスクカタログ評価シート」のリスクが十分であるか、財務管理部とヒアリングを行う。
財務管理部は、「リスクカタログ評価シート」に記載された状況の変化等がないかを確認の上、発生可能性、影響度、財務報告への影響の有無等を考慮しリスクを評価する。
随時、期首からの状況に変化がないかを確認する。
Ⅲ.全社的な内部統制の評価
1.全社的な内部統制の評価方法
「全社的な内部統制コントロールシート」の評価項目に不足がないことを確認の上で、各プロセスオーナー及び関係部署の管理者に対する質問、必要に応じた証拠証憑の閲覧により整備状況・運用状況を評価する。
2.全社的な内部統制の評価項目
財務管理部は、実施基準に記載されている42項目の評価項目を参考に「全社的な内部統制コントロールシート」の評価項目を決定し、組織の改編時などには随時見直しを行う。
尚、全社的な内部統制の評価項目(財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼす項目を除く。)のうち、前年度の評価結果が有効であり、且つ、前年度の整備状況と重要な変更がない項目については、その旨を記録することで、前年度の運用状況の評価結果を継続して利用することができる。
3.全社的な内部統制の評価ツール
「全社的な内部統制コントロールシート」を利用する。
親会社(当社)についてはシートの全項目における評価を行う。連結子会社については、適宜に評価項目が選定された連結子会社用のシートで評価を行う。
4.全社的な内部統制の評価対象事業拠点の選定
基本的には、すべての事業拠点を評価の対象とする。但し、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少である場合は、評価対象としない。また、評価対象外の拠点で重要な不備等が識別された場合は、当該不備等が発生した事業年度において評価対象に含めるものとする。
金額的影響の重要性が僅少であるとする基準については、次の要件の何れかにより判断するものとする。
| 1 | 連結決算において、連結消去後の税引前利益を金額の高い会社から順に積み上げ、累計金額が全体の95%に入らない事業拠点 |
|---|---|
| 2 | 連結決算において、連結消去後の売上高を金額の高い会社から順に積み上げ、累計金額が全体の95%に入らない事業拠点 |
金額的影響の重要性の判定は、負の数を含めた単純数値によるものではなく、絶対値による。
5.会計監査人との協議
評価対象から除外する事業拠点を選定した段階で、財務管理部と監査室は会計監査人と、その妥当性について協議する。
6.全社的な内部統制の有効性の判断
全社的な内部統制が財務報告に係る虚偽記載リスクを低減するために、以下の条件を満たしていることを確認し、有効性を判断する。
(1) 全社的な内部統制が、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠して構築されていること。
(2) 全社的な内部統制が、業務プロセスに係る内部統制の有効性を支援し、企業における内部統制全般を適切に構成している状態にあること。
Ⅳ.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価
1.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価方法
(1) 全社的な観点で評価すべき決算財務報告プロセスについては、「全社的な観点での評価シート」を用いて、各プロセスオーナー及び関係部署の管理者に対する質問、必要に応じた証拠証憑の閲覧により整備状況・運用状況を評価する。
(2) 個別の業務プロセスとして評価すべき決算・財務報告プロセスは、業務プロセスに係る内部統制の評価方法に準じて評価する。
2.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価項目
(1) 全社的な観点で評価すべき決算・財務報告プロセスは「全社的な観点での評価シート」の評価項目とし、財務管理部は必要に応じて見直す。
(2) 個別の業務プロセスとして評価すべき決算・財務報告プロセスは、「評価対象項目の識別リスト」により重要性を判断し、財務管理部が評価項目を選定する。
3.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価ツール
(1) 全社的な観点で評価すべき決算・財務報告プロセスは「全社的な観点での評価シート」を用いる。
(2) 個別の業務プロセスとして評価すべき決算・財務報告プロセスは、業務プロセスに係る内部統制の評価方法に準ずる。
4.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価対象事業拠点の選定
全社的な内部統制において選定した事業拠点とする。
5.財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等の選定
財務管理部は、有価証券報告書等における財務諸表以外の開示事項のうち、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等を、下記の項目より金額的、質的な重要性を勘案して選定する。
(1) 財務諸表の表示等を用いた記載
- ① 「企業の概況」の「主要な経営指標等の推移」の項目
- ② 「事業の状況」の「事業等のリスク」、「研究開発活動」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目
- ③ 「設備の状況」の項目
- ④ 「提出会社の状況」の「株式等の状況」、「自己株式の取得等の状況」、「配当政策」及び「コーポレート・ガバナンスの状況等」の項目
- ⑤ 「経理の状況」の「主な資産及び負債の内容」及び「その他」の項目
- ⑥ 「提出会社の保証会社等の情報」の「保証の対象となっている社債」の項目並びに「指数等の情報」の項目
(2) 財務諸表の作成における判断に密接に関わる事項
- ① 「企業の概況」の「事業の内容」及び「関係会社の状況」の項目
- ② 「提出会社の状況」の「大株主の状況」の項目における関係会社、関連当事者、大株主等の記載事項
6.会計監査人との協議
全社的な観点で評価すべき項目の範囲、評価方法等を定めた段階で、会計監査人と協議する。
7.決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価項目ごとの整備・運用状況の有効性の判断
(1) 全社的な観点で評価すべき決算・財務報告プロセスは、以下の点に留意する。
- ① 一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠して整備及び運用されていること。
- ② 個別の業務プロセスに係る内部統制の有効な整備及び運用を支援し、決算・財務報告プロセス全般を適切に構成している状態にあること。
(2) 個別の業務プロセスとして評価すべき決算・財務報告プロセスは、業務プロセスに係る内部統制の評価項目ごとの整備・運用状況の有効性の判断に準ずる。
Ⅴ.業務プロセスに係る内部統制の評価
1.業務プロセスに係る内部統制の評価方法
業務プロセスに係る内部統制の評価方法は、以下の整備状況の評価、運用状況の評価による。
尚、IT業務処理統制は、システムごとにシステム企画部担当者、キッセイコムテック(株)担当者が参加し、IT環境の変化を踏まえた上で、必要に応じ自動化統制の評価に問題がないかを確認する。
(1) 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の評価
整備状況の有効性の評価方法
- ① プロセスオーナー・担当者への質問、業務の観察及び証拠証憑の閲覧により、「業務フロー」「業務記述書」「職務分掌表」が、実状と相違ないかを確認する。
- ② 「リスク・コントロール・マトリクス」を査閲して、当該業務におけるリスクとそれを低減するためのコントロールの存在及び十分性を確認する。
- ③ 「RCM(整備状況評価シート)」に、コントロールの証跡、コントロールの十分性について、評価結果を記載する。
- ④ 内部統制の整備状況の評価は原則として毎期実施する必要がある。但し、全社的な内部統制の評価結果が有効である場合には、当該業務プロセスに係る内部統制(財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼすものを除く。)のうち、前年度の評価結果が有効であり、且つ、前年度の整備状況と重要な変更がないものについては、その旨を記録することで、前年度の整備状況の評価結果を継続して利用することができる。
(2) 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の評価
運用状況の有効性の評価方法
- ① プロセスオーナー・担当者への質問、証拠証憑の閲覧、再実施等により運用状況を確認し、「RCM(運用状況評価シート)」に評価結果を記載する。
- ② 運用評価におけるサンプリングは、以下の通りとする。
- ⅰ サンプリングの件数及び手法
サンプル件数は、全社的な内部統制の有効性に応じて決定する。
サンプリングは、無作為抽出により実施する。 - ⅱ IT業務処理統制における過年度評価結果の利用可否の判断
評価するシステムのうち、前年度の評価結果が有効であり、且つ、システムの変更はなく関連するIT全般統制が当年度も有効に運用されている場合には、前年度の運用状況の評価結果を継続して利用することができる。但し、システムの変更がないことを証明する必要がある。また、当該項目に係るIT環境に変化があった場合は、必要に応じて評価を行う。 - ③ 内部統制の運用状況の評価は原則として毎期実施する必要がある。但し、全社的な内部統制の評価結果が有効である場合には、当該業務プロセスに係る内部統制(財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼすものを除く。)のうち、前年度の評価結果が有効であり、且つ、前年度の整備状況と重要な変更がないものについては、その旨を記録することで、前年度の運用状況の評価結果を継続して利用することができる。
2.業務プロセスに係る内部統制の評価項目
業務プロセスごとにリスクの重要性を勘案し、評価対象とすべきコントロールを評価項目と定め、必要に応じて見直す。
3.業務プロセスに係る内部統制の評価ツール
評価ツールとして、「業務フロー」「業務記述書」「リスク・コントロール・マトリクス(RCM)」(整備状況評価シート)、(運用状況評価シート)」「職務分掌表」を利用する。
4.業務プロセスに係る内部統制の評価対象事業拠点の選定
(1) 重要な事業拠点の選定
| 1 | 重要な事業拠点の判断基準は、連結売上高とする。 |
|---|---|
| 2 | 連結消去後の売上高を金額の高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね3分の2に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点とする。 |
| 3 | 上記金額的影響の大きい事業拠点に加え、質的影響を考慮して必要に応じ重要な事業拠点とする。 |
(2) 事業拠点選定の妥当性(拡大の必要性)の判定、及び拡大の場合の方針・選定方法
| 1 | 全社的な内部統制の有効性に問題がある場合、業務プロセスに係る内部統制への影響を検討する。 |
|---|---|
| 2 | 全社的な内部統制の運用評価の際に、個別の事業拠点の有効性に問題がある場合は、当該事業拠点を追加対象とすることを検討する。 |
| 3 | すでに評価対象としている事業拠点の有効性に問題がある場合は、サンプリング件数を増やす等を検討する。 |
| 4 | 整備状況の不備及び全体へ影響する不備である場合は、是正措置を実施する。(業務プロセスの評価範囲を拡大する等の対応はしない) |
5.業務プロセスに係る内部統制の対象とする業務プロセスの選定
(1) 事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスのうち、財務報告に対する影響の重要性が僅少であるとして評価対象から除外するための判定
重要な事業拠点において複数事業を営んでいる場合で、重要な事業又は業務との関連が低く、財務報告に対する影響の重要性も僅少である業務プロセスは、評価対象から除外する。
(2) 個別に評価対象として追加する際の、重要な虚偽記載リスクの把握と業務プロセスの選定
財務管理部は、「リスクカタログ評価シート」において、リスクが高いとして認識された業務プロセスを、個別に評価対象として追加する。
6.会計監査人との協議
評価対象とする重要な事業拠点、業務プロセスを選定した段階で、財務管理部と監査室は会計監査人とその妥当性について協議する。
7.業務プロセスに係る内部統制の評価項目ごとの整備・運用状況の有効性の判断
(1) 整備状況の有効性の判断
以下の点に留意する。
- ① 内部統制は、不正又は誤謬を防止又は適時に発見できるよう適切に実施されているか。
- ② 適切な職務の分掌が導入されているか。
- ③ 担当者は、内部統制の実施に必要な知識及び経験を有しているか。
- ④ 内部統制に関する情報が、適切に伝達され、分析・利用されているか。
- ⑤ 内部統制によって発見された不正又は誤謬に適時に対処する手続が設定されているか。
(2) 運用状況の有効性の判断
業務プロセスに係る内部統制の評価方法に記載した評価方法による。
8.委託業務の評価
(1) 選定された業務プロセスにおける委託業務の識別
業務プロセスの中に委託業務があれば、評価対象とする。
(2) 財務報告への影響の判定(重要性の判定)
重要なコントロールが委託先の内部統制に依存している場合には、財務報告への影響は重要であるものと判定する。当社グループにおける業務プロセスに係る内部統制で、重要な虚偽記載リスクが低減できている場合は、委託先のコントロールの財務報告への影響は重要でないものと判定する。
(3) 財務報告への影響が重要であると判定された委託業務に係る内部統制の評価方法
委託先に対して、財務報告における重要な虚偽記載リスクが低減できる内部統制が構築されているか確認する。
委託先が別に受けた評価の報告書が利用できる場合はこれを確認し、利用できない場合は、当社が直接サンプリングにより確認する等の方法を検討する。
報告書を利用する際には、以下の点に留意する。
- ① 報告書における評価範囲が、当社の委託業務を含んでいること
- ② 報告書における評価手続が、適切と認められるものであること
Ⅵ.IT全般統制の評価
1.IT全般統制の評価方法
(1) IT全般統制については、評価領域(ドメイン)毎の統制活動に応じてシステムをグルーピングし、当該グループごとに評価を行う。
(2) 「リスク・コントロール・マトリクス」を確認した上で、各プロセスオーナー及び関係部署の管理者に対する質問、必要に応じた証拠証憑の閲覧により整備状況・運用状況を評価する。
(3) IT全般統制の項目(財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼす項目を除く。)のうち、前年度の評価結果が有効であり、且つ、前年度の整備状況と重要な変更がない項目については、その旨を記録することで、前年度の運用状況の評価結果を継続して利用することができる。但し、当該項目に係るIT環境に変化があった場合は、必要に応じて評価を行う。
2.IT全般統制の評価項目
「リスク・コントロール・マトリクス」の評価項目とする。
3.IT全般統制の評価ツール
「リスク・コントロール・マトリクス」を評価ツールとする。
4.IT全般統制の評価単位の評価
評価範囲として選定された業務プロセスにおいて、システムによる自動化された業務処理がある場合は、当該システムの評価領域(ドメイン)の状況を把握し、その概要を基にIT全般統制の評価単位とする。
5.会計監査人との協議
評価対象とするIT全般統制の評価単位を定めた段階で、財務管理部と監査室は会計監査人と、その妥当性について協議する。
6.IT業務処理統制の評価作業に係るIT全般統制の有効性の判断
IT全般統制の整備・運用状況が有効であれば、ITに係る業務処理統制の運用評価のためのサンプル数は、最低限の1件とする。
Ⅶ.不備の検討
1.不備の影響額の推計及び集計
全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制、業務プロセスに係る内部統制、IT全般統制のそれぞれに「不備一覧表」を作成の上、改善されない場合には不備の影響額の推計及び集計を行う。
(1) 全社的な内部統制
- ① 内部統制に不備があった場合は、「全社的な内部統制コントロールシート」に不備の内容を記述し、「不備一覧表」を作成する。
- ② 発見された不備を基本的要素ごとに評価した結果、その基本的要素が有効でないと判断された場合、それが他の基本的要素に与える影響を考慮する。
- ③ 業務プロセスを適切に支援していない不備があり、その不備が業務プロセスに影響を与える場合は、その影響の内容・重要性を把握する。
(2) 決算・財務報告プロセスに係る内部統制
- ① 内部統制に不備があった場合は「全社的な観点での評価シート」に不備の内容を記述し「不備一覧表」を作成する。
- ② 個別の業務プロセスとしての決算・財務報告プロセスに不備があった場合は、業務プロセスに係る内部統制に準ずる。
(3) 業務プロセスに係る内部統制
- ① 内部統制に不備があった場合は「RCM(整備状況評価シート)・(運用状況評価シート)」に、不備の内容を記述し「不備一覧表」を作成する。
(4) IT全般統制に係る内部統制
- ① 内部統制に不備があった場合は「RCM(整備状況評価シート)(運用状況評価シート)」に、不備の内容を記述し「不備一覧表」を作成する。
2.開示すべき重要な不備
開示すべき重要な不備とは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備をいう。
(1) 全社的な内部統制における開示すべき重要な不備
全社的な内部統制における不備のうち、開示すべき重要な不備は以下の通りとするほか、開示すべき重要な不備が及ぼす金額的な面及び質的な面の双方について検討を行い判断する。
- ① 経営者が財務報告の信頼性に関するリスクの評価と対応を実施していない。
- ② 取締役会又は監査役会が財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用を監督、監視、検証していない。
- ③ 内部統制の有効性を評価する責任部署が明確でない。
- ④ 財務報告に係るITに関する内部統制に不備があり、それが改善されずに放置されている。
- ⑤ 業務プロセスに関する記述、虚偽記載のリスクの識別、リスクに対する内部統制に関する記録など、内部統制の整備状況に関する記録を欠いており、取締役会又は監査役会が、内部統制の有効性を監督、監視、検証することができない。
- ⑥ 経営者や取締役会又は監査役会に報告された全社的な内部統制の不備が合理的な期間内に改善されない。
(2) 決算・財務報告プロセスに係る内部統制における開示すべき重要な不備
全社的な観点で評価すべき決算・財務報告プロセスにおける不備のうち、開示すべき重要な不備は以下の通りとするほか、開示すべき重要な不備が及ぼす金額的な面及び質的な面の双方について検討を行い判断する。
- ① 会計処理の文書化、会計方針及び手続きに係る不備
- ② 経理の人材の厚み、能力、教育に係る不備
- ③ 会計監査人の指摘による重要な修正
- ④ 過年度財務諸表の修正
個別の業務プロセスとしての決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備は、業務プロセスに係る内部統制における開示すべき重要な不備に準ずる。
(3) 業務プロセスに係る内部統制における開示すべき重要な不備
業務プロセスに係る内部統制における開示すべき重要な不備とは、内部統制の不備のうち、一定の金額を上回る虚偽記載又は質的に重要な虚偽記載をもたらす可能性が高いものをいう。
- ① 金額的な重要性
連結消去後税引前利益の概ね5%程度を基準値とするが、財務諸表監査における金額的重要性との関連に留意しつつ、会計監査人と協議して適切に判断する。 - ② 質的な重要性
上場廃止基準、投資判断に与える影響の程度、関連当事者との取引、大株主の状況に関する記載事項などが財務報告の信頼性に与える影響の程度で判断する。
(4) IT全般統制における開示すべき重要な不備
IT全般統制における開示すべき重要な不備とは、IT全般統制における不備のうち、ITの有効な運用を継続的に維持することができない不備をいう。
3.開示すべき重要な不備に関する判断
内部統制の不備が複数存在する場合には、それらを合わせて、開示すべき重要な不備に該当していないかを評価する。
複数の不備を合わせて開示すべき重要な不備になる場合とは、以下の通りとする。
(1) 同じ勘定科目に関係する不備をすべて合わせると、当該不備のもたらす影響が財務報告の重要な虚偽記載に該当する場合
- ① 複数の不備が一つの勘定科目に与える影響を合わせると開示すべき重要な不備に該当する場合
- ② 複数の事業拠点の不備が、全体で開示すべき重要な不備に該当する場合
(2) 集計した不備の影響が勘定科目ごとに見れば財務諸表レベルの重要な虚偽記載に該当しない場合でも、複数の勘定科目に係る影響を合わせると重要な虚偽記載に該当する場合
4.不備の報告方法
監査室は、開示すべき重要な不備及び報告すべきと判断される不備について、会長、監査役、リスク管理委員会に報告する。
リスク管理委員会は、開示すべき重要な不備について取締役会に報告する。
Ⅷ.開示すべき重要な不備等の是正
1.是正計画の策定
監査室は、それぞれの「不備一覧表」に改善策として記載されているもののうち、開示すべき重要な不備について是正計画として取りまとめ、会長、監査役、リスク管理委員会に報告し、リスク管理委員会は取締役会に報告する。
2.是正作業の実施方法
各主管部署及び関係部署は、是正計画に基づき内部統制の構築に準じて是正作業を実施する。
3.是正結果の報告方法
監査室は、各主管部署及び関係部署から報告された是正結果を評価し、その結果を会長、監査役、リスク管理委員会に報告し、リスク管理委員会は取締役会に報告する。
Ⅸ.再評価等の追加手続
1.期中に評価を実施した場合の期末日までの重要な変更の確認方法
期末日までに重要な変更がないことを各主管部署への「内部統制期末日現在の確認書」にて確認する。
2.重要な変更に対する追加の評価手続の検討
期中での評価実施後、重要なコントロールに変更が行われた場合、追加の評価手続を検討する。
3.再評価の対象範囲
再評価の対象はコントロールの変更により影響のある部分のみとする。
4.再評価の方法、件数等
再評価はコントロールの頻度に合わせて、必要と認められる件数を評価する。
5.期末日の確定数値を基にした評価範囲、重要性の基準値の確認
(1) 期末日の確定数値を基に評価範囲の妥当性を確認する。
(2) 重要性の基準値に変更があった場合には、期末日の確定数値を基に重要な欠陥の判断に影響がないかを確認する。
6.期末日後から内部統制報告書提出日までの是正及びその有効性の確認
期末日後に是正措置が講じられる場合、その内容及び有効性について、通常の評価方法に準じて確認を行う。
Ⅹ.評価作業の実施が困難であるとして評価対象から除外する方針
やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できない場合には、当該事実が財務報告に及ぼす影響を十分に把握した上で、評価範囲から会計監査人と協議の上、除外する。
例えば、以下の場合には、やむを得ない事情があると判断する。
(1) 下期において他企業を買収した場合又は合併した場合
(2) 災害が発生した場合
ⅩⅠ.内部統制報告書
(1) 監査室は、内部統制報告書(案)を作成し会長に報告する。
(2) 内部統制報告書の記載様式は、内閣府令を遵守する。
ⅩⅡ.記録及び保存
監査室は、内部統制の有効性の評価手続き及びその評価結果、並びに発見した不備及びその是正措置を記録し保存しなければならない。
記録及び保存に当たっては、後日、第三者による検証が可能となるよう、関連する証拠書類を適切に保存する。
内部統制について作成した記録の保存の期間は、文書管理規程により定める期間とする。
保存の方法は、磁気媒体、紙又はフィルム等のほか必要に応じて適時に可視化することができる方法により保存する。
2008年1月17日制定
2024年4月1日改正実施
公的研究費の管理・監査のための実施基準
1. 目的
本基準は、キッセイ薬品工業株式会社(以下、会社という)が、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人(以下、資金配分機関という)から配分される公募型の研究資金等の競争的資金(以下、競争的資金等という)を、文部科学省が制定した「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下、ガイドラインという)に基づき適正に管理することを目的として制定する。
2. 組織と役割
2.1 責任体系
会社は、ガイドラインに定める競争的資金等の運営、管理に関する体制を以下のとおり定める。
| 最高管理責任者: | 社長 |
|---|---|
| 統括管理責任者: | 開発本部長 |
| 公的研究費コンプライアンス推進責任者: | 研究本部研究統括部長 開発本部開発推進部長 財務管理部長 |
2.2 権限及び責任
各責任者の具体的な権限及び責任は、以下各号の他は会社の諸規定の定めに従う。
1) 最高管理責任者は、会社全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。また、統括管理責任者及び公的研究費コンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について関係部門全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。また、競争的資金等の運営・管理について不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任を持ち、関係部門全体の不正に係る情報を確認するとともに、不正発生時にはその状況を最高管理責任者に報告する。
3) 公的研究費コンプライアンス推進責任者は、各部門における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。また、統括管理責任者の指示の下、当該部門における不正防止対策を実施し、その実施状況を統括管理責任者に報告する。不正防止を図るため、各部門における競争的資金等の運営・管理に関わるすべての研究者及び事務職員(以下、構成員という)に対して、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。当該部門において、構成員が適切に競争的資金等の管理・執行を行っているかモニタリングし、適切に競争的資金等の管理・執行が行われていない場合は、改善指導する。
3. 環境の整備
会社は、競争的資金等の運営・管理の体制につき、会社法による内部統制体制及び金融商品取引法による財務報告の信頼性にかかる体制下で、以下各項の条件を含む適切な環境整備を行う。
3.1 職務権限
競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任については、別途定める組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に従う。
3.2 構成員の行動規範
構成員は、競争的資金等の運営・管理において、研究費が公的資金であり、会社による管理が必要であるという原則とその精神を理解し、専門的能力をもって公的資金の適切な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務処理を行わねばならない。
3.3 コンプライアンス教育
各部門の公的研究費コンプライアンス推進責任者の指示により、開発本部開発推進部臨床管理室臨床管理グループは、構成員にコンプライアンス教育(競争的資金等に関する会社のルール等)を実施し、受講状況及び理解度を確認する。また、受講の機会等(構成員の更新時等)に構成員より誓約書を入手する。
4. 研究費の適正な運営・管理
1) 競争的資金等の管理については、以下の規程の他、本基準を含む社内諸規定に従う。なお、構成員は、取引先との公平・公正な取引及び調達を行うことを行動原則とする。
- · 財務報告に係る内部統制構築・評価の基本方針書
- · 組織規程
- · 職務権限規程
- · 業務分掌規程
- · 予算管理規程
- · 契約等関連業務管理規程
- · 内部監査規程
- · 購買規程
- · キッセイ薬品購買方針
- · 購買担当者行動ガイドライン
2) 物品等の発注時には、当該発注先との契約に従い、発注部署が適正に行う。なお、当該発注先との契約締結時には、事前に法務部による契約の審査を受けた後、適切な権限を持つ者の決裁を得る。
3) 物品等の検収は、別途定める検収部署があらかじめ取り決めた規格書、納入仕様書等に基づいて行う。
4) 不正な取引に関与した業者は、当該業者との契約の解除権を行使して取引停止とするとともに、損害賠償請求権を行使する。
5) 構成員は、別途定める「経費精算に関する留意事項」に従い、経費の管理を行う。
6) 開発本部開発推進部臨床管理室臨床管理グループは、予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。また、予算執行が当初計画に比較して著しく乖離している場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、必要に応じて改善策を講じる。
5. 不正防止対策
5.1 不正を発生させる要因等の把握と不正防止計画の策定
会社は、金融商品取引法による財務報告の信頼性にかかる体制を統括管理する財務管理部の下に、競争的資金等の利用に関する不正を発生させる要因の把握と不正防止計画を策定する。
5.2 不正防止計画の実施
1) 財務管理部財務経理課、研究本部研究統括部研究企画グループ及び開発本部開発推進部臨床管理室臨床管理グループ(以下、防止計画推進部署という)は、協同して競争的資金等の不正防止計画の推進を行い、実施状況を確認する。
2) 最高管理責任者は、率先して不正防止を推進し、自ら不正防止計画の進捗管理に務める。なお、最高管理責任者が率先して不正防止を推進することは会社内外に公表する。
5.3 不正に関する調査及び懲戒
会社は、競争的資金等の使用に際し、構成員等による不正が認められた場合には、懲戒委員会にて事実関係を調査し、社長の決定により懲戒する。なお、必要に応じ、懲戒委員会に替え特別プロジェクトチームを設置する。
5.4 告発等の取り扱い
会社は、通報(告発)を受け付けた場合、コンプライアンス・プログラム規程に基づき調査し、ガイドラインに従って資金配分機関へ報告する。
6. 情報の伝達
1) 競争的資金等の使用に関するルール、事務処理手続き等について会社内外からの相談を受け付ける窓口を以下に設置する。
研究本部研究統括部研究企画グループ TEL:0263-82-8820
開発本部開発推進部臨床管理室臨床管理グループ TEL:03-5684-3596
財務管理部財務経理課 TEL:0263-25-9651
2) 競争的資金等の使用に関するルール等について会社内外からの通報(告発)を受け付ける窓口を以下に設置する。
法務部コンプライアンス推進室コンプライアンス課 TEL:0263-25-9081(代表)
田中・吉久保法律事務所 TEL:03-3230-0137
久保田法律事務所 TEL:0263-32-0610
3) 相談及び通報を受け付けた担当者は、不正に係る情報を得た場合、速やかに最高管理責任者へ報告する。
4) 競争的資金等の不正への取り組みに関する会社の方針及び意思決定手続きを資金配分機関へ報告することにより、公表に代える。
7. モニタリング
会社は、競争的資金等を利用する活動が諸規定に従い適正に行われているか、また組織、職制、社内手続及び内部監査を通じ経営目的達成のため合理的に運営されているかを、モニタリングする。
8. 社内監査
会社は、競争的資金を利用する活動の会計手続及び会計証憑書類の作成・保管等が、適正に行われているか内部監査規程に従い、毎年度監査を実施する。なお、内部監査部門は、防止計画推進部署及び会計監査人と連携して業務にあたる。
9. 文部科学省等によるモニタリング
開発本部開発推進部臨床管理室臨床管理グループは、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、文部科学省等に書面により報告を行う。会社は、ガイドラインに基づく文部科学省の調査(書面、面接、現地調査)について協力するものとする。なお、調査の結果、問題が指摘された場合は、速やかに改善計画を作成し、同計画を実施する。
2009年3月26日制定
ただし、本基準は2008年12月24日に遡って適用されるものとする
2017年4月1日改訂